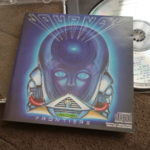こんにちは。熊の実です。
これまでにいろいろなアボカドの種で発芽実験をしてきました。水栽培が根の出方などの観察に向いているので、最初は水栽培から始めて、根が出てきたら土に植えるということを繰り返してきました。

こんにちは。熊の実です。 前の記事では果肉の多いアボカドの選び方について独自の検証結果を紹介しました。 以下の記事では発芽しやすい種の特徴について独自の研究結果を紹介したいと思います。 食べたあとに種が残ります。この種まで全部食べてしまうか、発芽させて観葉植物として楽し...
しかし、寒い時期だったので、元々発芽しにくい条件でした。それでも、同じ条件において、小さい種の方が発芽しやすいという感触は得ることができました。また、せっかく発芽しても、芽の先端は寒さで枯れてしまいました。もう3月でいろいろな種が発芽する季節になりました。ここで、最初から土を媒体として、これまでに得られた知見が正しいかどうかを同じ容器に寄せ植えして検討してみようと思います。
プランターに寄せ植えした14個
そこで用意した種が冒頭の写真に示した14個です。水栽培で様子をみてきたけれども発根しなかったものも含みます。これは、水栽培でだめだと判断したものを土に植えてみたら変化が見られたものもあるから、いわゆる敗者復活戦です。
時系列順になるようにアルファベットを付けています。Cが一番古いです。一部、前後しているものもあります(例えば、Nは時系列ではQとRの間になります)。Cのみニュージーランド産で、あとはすべてメキシコ産です。

上段の左から4つ(J, C, D, F)が水栽培で変化が少なかったものです。ただし、Cは最近、亀裂が広がってきて種自体が卵ケースの穴より大きくなっていました。それに対して、J, D, Fはほとんど変化が見られなかった種です。
土に植える前の状態
J, C, D, F以外は新規に用意した種です。3月1日に土に植えるまでは、水に浸していましたが、C以外はほとんど変化はありません。
アボカドの種J, C, D, F, H, I(上段左からD, F, H, 下段左からJ, C, I)

アボカドの種K, L, M, N, O, P, Q, R(上段がO, P, Q, 下段がK, L, M, その下がN, R)

土に植えました
これらを百均のダイソーで買ってきたプランター1個に寄せ植えしました。けっこうぎゅうぎゅう詰めです。このプランターは受け皿とセットで108円でした。コスパ抜群です。しかし浅いのでこのまま発芽したとしてもまた植え替えが必要なのは明らかです。まあ、その時はその時ということで、この14個ができるだけ同じ条件下に置かれるようにするために、このような方法をとりました。土はタネのタキイの「野菜と花の培養土」を用いています。
種の皮の影響
また、これまでの実験ではほとんどの種の皮は除去していました。その理由は、
1. 種が割れる挙動がわかりやすかったこと
2. 先天的に種の割れ目の入り方が不自然なものが時々あるのですが、それは皮を剝かないとわからないこと
3. 種の色の変化も発根の判断において重要な情報になったこと
です。例えば、水栽培で根が出て来ると、クロロフィルが合成されて種が緑色になってきました。このような変化が皮がない場合はわかりますし、皮がない方が光が当たって好都合だからです。
しかし今回の実験ではあえて皮はそのままにして植えたのが6個と、半分剝いた種が1個で、ちょうど半数になります。皮は初期の変化にはあまり影響しないのではないかというのが私の予想です。今回は土に植えたので発根したかどうかもわかりにくいです。これまでの水栽培では、種が割れてくるのも底部からで、頂部から割れることはありませんでした。ほとんどの場合、頂部は閉じていました。それを底部が広がってきてから人為的にカッターで割れ目に沿って切ってやったり、最初から頂部と底部を切り落としていました。
種の変化の判断方法
今回は土に植えたので、発芽しそうかどうかの判断方法は、
1. 種の亀裂が広がってくるかどうか
2. その亀裂の間から芽が出て来るかどうか
3. 皮を剝いてある種は、表面が緑色になってきているかどうか
ぐらいしかありません。土の中の様子はわからないからです。その点、水栽培は手でつまんで詳細な観察もできるのでわかりやすいです。でも、土の方が種に与える影響はいいものがあると何となく私は感じているので、今回はこのような方法をとりました。
発芽予想
これまでの知見に基づいて発芽予想をしてみたいと思います。H, I, O, P, Qは発芽しそうな気がします。Jは厳しいと思います。でも、土に植えたことで好転することもありえるので、見てみたいと思います。Cは発芽すると思います。すでに土に植える時点で兆しが見えたからです。ほかの大きめの種は何ともいえませんが、少なくとも、変化が見られる時期は小さい種よりは遅いと見ています。
以上が私の予想です。この続きはこの記事の下に随時追加していきます。予想が大きく外れたら笑ってください(笑)。でも外れても「失敗」ではなく「新しい知見」ですので、それはそれでいいです。予想するのは楽しいですし、それがサイエンスです。
2017年4月30日現在の結果
芽が出てきている種はありませんが、Hは割れ目の隙間から芽が確認できました。種Jは割れることができないので芽は出て来れないような気がします。しかし、それ以外の種は遅かれ早かれ芽は出て来ると思います。根はすべての種で出てきています。なぜならば、種を動かそうとしても動かないことと、種の下半分が割れてきていることから判断できるからです。実際にC, D, L, M, Nあたりの鉢の下から根が出てきています。
これらのことから、まず根が出てきて、そのあと芽が出て来ることがわかります。芽が出やすいようにするためには、種の頂部を数mmほど切り落としてやればいいと思います。しかし、一度植えて根が出てからは切り落とすのが難しいので、植える前に切り落としておくのがよいと思います。種の底部は切り落としても切り落とさなくてもいいような気がしますが、ちょっと変わった形の底部をもつ種は切り落としてやった方がいいような気がします。
まだ根がでていなかったアボカド
2017年5月11日に一回り大きなプランターに植え替えました。
すべてのアボカドの種の中で、まだ根がでていなかった種はDとIでした。数ミリだけ表面に出てきていたのがRでした。そのほかの種は根がけっこう出ていました。しかし、根が出ていても発芽しないのではないかと考えられるのはJです。すでに芽が出てきているのはHとLです。
やはり、水栽培で根が出ていることを確認した後で土に植えた方が確実だと思います。DとIのような種は掘り起こさない限り判断が難しいです。種を少し動かして固定されているかどうかでもわかるとは思いますが、まだ短い根しか出ていない場合、切れるかもしれません。土の中の様子は掘り起こさないとわからないので非破壊的な判断にはどうしても限界があります。
2017年5月15日夕方、すべての種をチェックして、まだ頂部がくっついている種にカッターで割れ目に沿って切り込みを入れました。これで、芽が出て来る時に邪魔になりにくいです。その時気づいたのですが、種K(左下)は根が2本出て2cmほどになっていたのですが、グラグラ動いたので持ち上げてみたら腐っていました。そのまま埋め戻しました。

植え替えてから2週間後の発芽状況
2017年5月25日現在、芽が伸びてきました。
まとめ
今回の実験でわかったことは、
1. 発芽しても冬の寒さで枯れてしまうので、植えるのは冬前ではなくて春がよく、日当りのよい場所に置くと発芽しやすいということ、
2. 水栽培で発根させておいて土に植えるのが確実だけど、春であればいきなり土に植えてもかなりの確率で根が出て来ること、
3. 今回の寄せ植えでは大きくて丸い種も、小さめのどんぐり型の種も根は出てきていること、
4. 種の皮をつけたまま植えた種のうち、皮を剥がしてみたら腐っていた種もあったので、皮は剥いで植えた方がよさそうということ、です。
よって、奇形の種は底部から発根はできるものが多いものの、頂部が割れにくいと判断できるものは発芽が難しいといえます。正常な形をした種であれば、植える季節を選びさえすれば高い確率で発芽すると結論付けられます。確実性を上げたければ、あらかじめ水栽培で発根させておいてから土に移すのがよいと思います。種の頂部と底部は切ってやった方が立体的な障害が少ないので発芽しやすい感じです。切ったことによって養分が少なくなり発芽しにくいということはなさそうです。
種の頂部が閉じていて、芽が出てきにくいと思われた4個には爪楊枝を挟んでみました。これで様子を見てみます。若干奇形気味だったJからも芽が出てきました。
今回の検討結果では、種の大小とか形から発芽のしやすさ・しにくさを判断するのは難しそうです。ざっくり言うと、アボカドは暖かい季節には発芽率は高いといえそうです。また、種は双葉(子葉)のようなもので、根が張ってくるとクロロフィルが生成するようです。そういう意味では種も観賞の対象になりそうです。
それでは、また。

こんにちは。熊の実です。 前の記事では果肉の多いアボカドの選び方について独自の検証結果を紹介しました。 以下の記事では発芽しやすい種の特徴について独自の研究結果を紹介したいと思います。 食べたあとに種が残ります。この種まで全部食べてしまうか、発芽させて観葉植物として楽し...
追記
2017年6月13日現在、発芽していないのはDとFとOの3個だけになっています。Oについては、発芽しかけていたのですが、先端が枯れた形です。発芽したと思ったら生長末端が枯れてしまうパターンは意外に多いです。必ずしも寒くはないのに起こります。一つの原因として殺虫剤の使用を疑っています。アブラムシが付くので市販の殺虫殺菌剤を噴霧することがあるからです。でも、よくわかっていません。いずれにしても発芽が始まったからといってうまく生長するとは限らないので予断は許しません。
おそらくこれら3個はこれ以上発芽しないような気がします。
Cは一度潰れた芽の枝として数本出てきました。KとRは割れ目からやっと芽が頭を出しました。
2017年7月1日現在、予想に反して発芽しないと思われたOは発芽して10cmほど伸びています。先端付近にアブラムシが付いていました。殺虫剤を使用すると若葉が枯れてしまうので指で全部潰しました。DとFは発芽していません。よって、今回の試みではDとFだけが発芽できませんでした。大きくて丸い種は小さい種より発芽しにくい傾向があるというのは確かだと思います。
発芽した種O(2017年7月1日現在)

だいぶ繁ってきました。発芽実験はこれで終わりですが、処分するのはもったいないので、畑に植えてみようと思います。冬には枯れると思います。(2017年7月1日現在)

2017年7月1日、実家に持って帰りました。

2017年7月1日、地植えしました。アボカドの根はあまり張っていません。

2017年7月2日、葉っぱが混み合っています。そのまま様子を見ます。タヌキが掘り返してしまう可能性が高いです。

2017年7月14日現在、発芽しないと思われていた種Fが発芽していました。しかし、先端が切れてしまっています。原因不明。

2017年7月14日現在、上から見た写真

結局、発芽しなかったのは種Dだけとなりました。今回の結果からわかることは、アボカドの種は気長に待てばかなりの高確率で発芽するということです。
2017年12月2日現在、まだきれいな緑色の葉っぱです。このあと2018年1月26日までの間に枯れてしまいました。

2018年1月26日現在、すべて枯れています。1月の大寒波もあり、寒さに耐えられなかったようです。仮に大寒波がなくて通常の寒さだったとしても枯れてしまった可能性は高いと考えています。



 アボカドの種14個の発芽状況
アボカドの種14個の発芽状況










 爪楊枝はプランターの右側の方(この写真では奥の方)に3本集中しています。植えた場所が影響しているとは思いませんが・・・
爪楊枝はプランターの右側の方(この写真では奥の方)に3本集中しています。植えた場所が影響しているとは思いませんが・・・