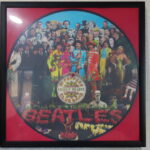こんにちは。熊の実です。
2017年2月2日(木)の「カミングアウトバラエティ 秘密のケンミンSHOW」で鹿児島弁についてやっていました。
「わいは、ぎをいうな。てけてげせんじ
いっだましいいれんか、やっせんぼう」
「おまえは文句を言うな。いい加減にせずに、魂をこめてしろ。臆病者が」
といった感じの意味です。水泳の宮下純一氏とか、元サッカー日本代表前園真聖氏とかが「カミングアウトバラエティ 秘密のケンミンSHOW」の中で上記の文章を鹿児島弁で読んでいました。
でも、私の住んでいた薩摩郡では、「やっせんぼう」は少なくとも私のまわりでは「やっせんぼ」でした。このように地域によって微妙な違いがあることが多いです。
私の田舎ではこう言うかもしれません(私だけの可能性もあり)
「わいが、ぎをかえたが。
てけてげせんじ、いっだましいれんか。
やっせんぼが。」
みたいな感じです。テレビで出ていたのとは微妙に違いますが、実際のところは住んでいる地域によって若干の違いがあるし、同じ地域でも個人単位でも若干の違いがあります。
では、なぜそれでも意味が通じるのでしょうか。
それにはいくつか押さえるべき重要なポイントがあります。(ちなみに、よく、ネット上で「抑える」という漢字を使ってあるのを目にしますが、この意味では「押さえる」ですよね!)
まず重要なのはイントネーションです。語尾が上がっているのか、下がっているのかで全然意味が違ってきます。
例えば、「じゃっど」は「そうだ」という意味です。語尾を下げて「じゃっど」といいます。しかし、「じゃっどん」は語尾を下げては言いません。「じゃっどん」は例外なく語尾を上げて言い、意味は「しかし」「そうは言っても」です。逆接の接続詞になります。
次に重要なのは文脈です。何の脈絡もなしにいきなり話されたらかなり難解だと思います。また、文字情報だけでもかなり難解です。
例えば、鹿児島弁で「へ」といえば、一般には「灰」「蠅」「屁」の3つのうち、どれかです。
でも、これら3つは全然違うものです。だから、状況とか文脈で判断します。
「ヘがトンジョッ」といえば「ハエが飛んでいる」、「桜島ンヘがフッデケタ」といえば、「桜島の灰が降り出した」、「ヘをヒッタ」といえば「おならをした」となります。
実際は省略された語がよく使われます。たとえば「こけけ」は「ここに来い」です。
でも対面で話せばニュアンスが伝わり、意味がわかります。語尾が上がれば疑問とか、下がれば肯定とか、いろいろ総合的に判断できます。
だから、若者がじいさんばあさんの言葉をだいたい「何を言いたいのか」理解できるのは、文脈(context)も含めてそのあたりのことが大きいと思います。
もともと鹿児島弁は盗み聞きされても意味がわからないように作られた言語だと聞いたことがあります。しかし、この説については、言語学関連の学会では肯定的に取り上げられたことはないとのこと。でも、そう言いたくなるくらい、難解な言語であることは確かです。
ちなみにKagoshima dialectとWeblioで引くと、
薩隅方言(さつぐうほうげん)は、鹿児島県(奄美群島除く)で話される日本語の方言。
となっています。
私も鹿児島を離れてもうだいぶなるので、話す相手もいないので日常で使わないため、だんだん単語を忘れてきました。でも、今住んでいる所でも相手がいると不思議とスラスラ話すことができます。鹿児島弁の最重要ポイントはイントネーションと言っても過言ではありません。それが意味を含んでいます。じいさんばあさんの言葉でも今でも聞けば意味はわかります。五感で感じ取るところがけっこう大きいのでしょう。だから、大河ドラマで鹿児島出身でない人が鹿児島弁をしゃべるとどうしても不自然さがあるのですぐわかります。こればかりはちょっとしたことでわかるので、他県出身者がいくら練習をしても完全にマスターすることは普通は無理だと思います。
それでは、また。
(クリックするとそのページに飛びます)

こんにちは。熊の実です。 西郷どんは「せごどん」と読みます。 「さいごうどん」なのですが、地元民、特に年配の人は「せごどん」と呼ぶことが多いです。もちろん、普通にさいごうどんとも言います。でも、ほとんどの若い子たちは「さいごうどん」と読むかもしれません(未確認ですけど)。 ...
(クリックするとその文字が先頭の単語一覧表に飛びます)